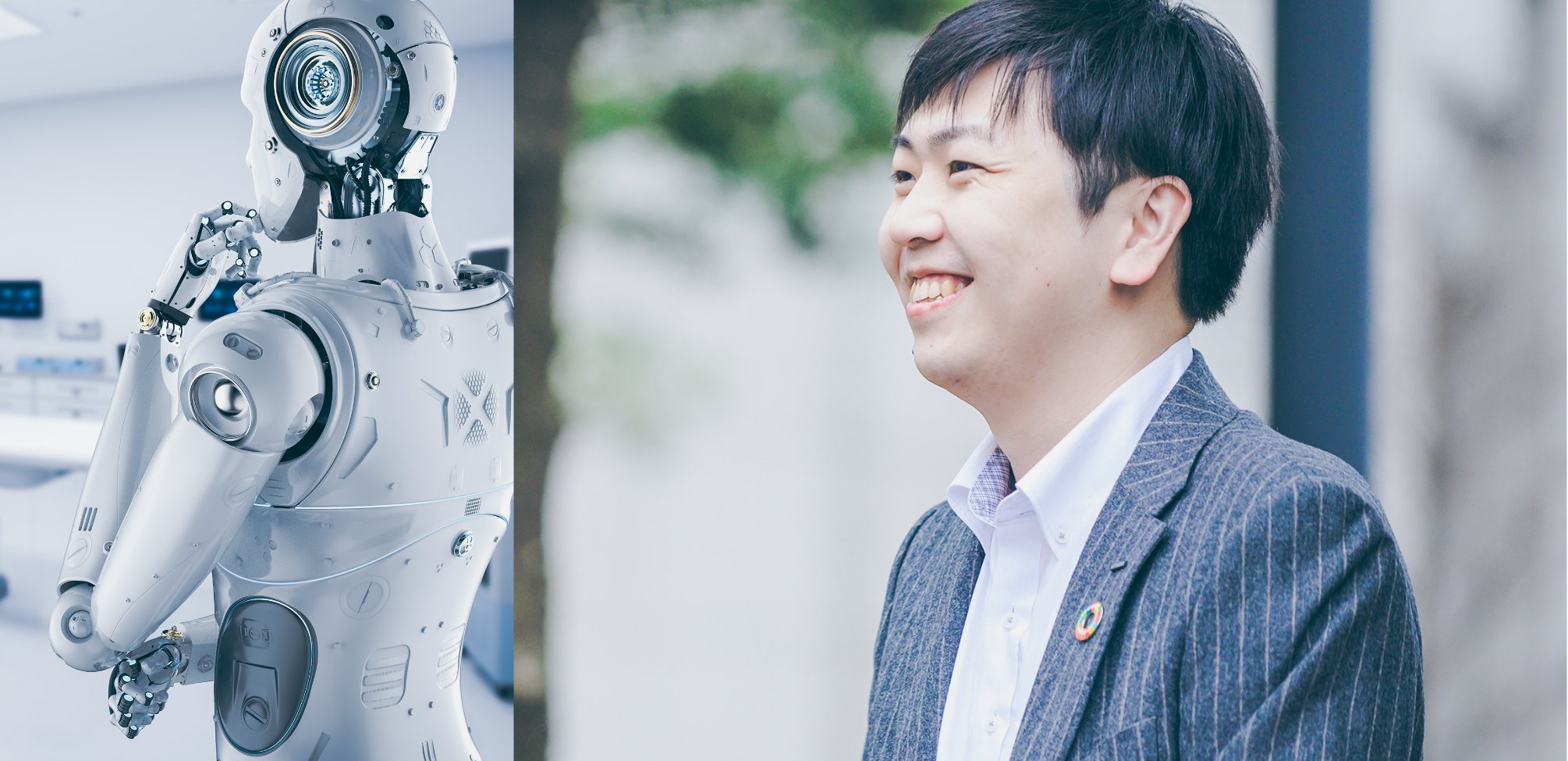
Q1プロジェクトにおける
あなたの役割とは?
本プロジェクトに参画する以前は、別の担当でアジャイル開発の普及・展開や新規R&Dの立ち上げを担当していました。そして2020年4月のヘルスケアAIセンタ設立と同時に異動し、本プロジェクトに参画しました。以前から顔面神経麻痺の共同研究が進められるという話は耳に挟んでおり、興味を持っていました。
このプロジェクトの特長は、メンバーがそれぞれ異なるキャリアや強みを持っていることです。AI開発は荒木、契約交渉は小倉が担当し、私はオンラインで開発を実施するための環境構築を担当することになりました。
環境構築、具体的にはAI開発に必要なリソースの準備、環境の運用などを対応しています。また、共同研究先への情報セキュリティに関する取組内容の説明や、ニュースリリースおよび新聞取材など対外発信も小山田と共に担当しました。
時系列的に紹介すると、2020年5月から6月にかけて新型コロナウイルス感染拡大による方針変更を受けた開発方法の再整理。7月から10月にかけて開発環境設計と共同研究先関係者への説明。11月から12月にかけて開発環境の構築と実証試験に向けた準備といった流れで対応しました。
Q2プロジェクトのなかで感じた
“BORDER”とは?
やはり新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた方針変更により、フルオンラインでプロジェクトを進めることになったことです。最大の問題は、プロジェクトの特性上開発に不可欠な個人情報データの取り扱いです。当初は患者動画を用いた実証は附属病院内で行う予定でした。一般に、情報セキュリティの強固さとデータの使い勝手の良さはトレードオフです。データを外部から扱えるようにすれば当然リスクは増大するので、情報を保護する環境を整備する必要があります。
そこで、個人情報データの取り扱いについて共同研究先と何度も話し合い、セキュリティレベルの高い環境を整備して、なんとかオンラインで開発が可能な状態を創り上げていきました。具体的には、クラウドサービスを活用して、共同研究先が持っている開発用サーバにオンラインでアクセスするための環境を構築しました。これにより、我々が手元に個人情報データを保持することなく開発を行っています。

また、オンラインでプロジェクトを進めていくに当たっては、開発の考え方や進め方そのものを変える必要も生じます。そのため、コミュニケーションツールやタスク管理ルールの整備など、オンラインでも円滑にプロジェクトが進行するような仕組みをつくることにも力を注ぎました。
Q3“BORDER”を超えたと
感じた瞬間は?
フルオンラインでの開発環境の構築というと大がかりに聞こえるかもしれませんが、実は環境構築自体は難しいものではありません。むしろ問題はオンライン環境でのプロジェクトの運用です。いかにスムーズなコミュニケーションをとるのか、最新情報に基づいた問題意識の共有をどのように行うのか。プロジェクト発足当時は試行錯誤の連続でした。
現在は、チーム内ではチャットや音声通話、チケット管理ツール、wikiなどの情報共有ツールの利用が浸透していて、様々な形でコミュニケーションを取れるようにしています。また、定期報告は朝会、夕会で行いますが、緊急要件が発生した場合はテレビ会議でメンバーを参集するなど、現在はさまざまなツールを使い分けることにより、プロジェクトの進め方もスムーズになっています。
一方、共同研究先である大学側に、オンラインでプロジェクトを進めることや、そのために開発手法を変えることに関して理解を得ることが大変でした。とくに個人情報データをオンラインで扱うケースは、大学側にとって前例が少なく、倫理審査委員会の承認を得るために各所に意見照会するなど、課題を一つ一つ解消していくことで、無事に実証試験に向けた環境構築が完了しました。
Q4これからチャレンジしてみたいことは?
このプロジェクトは研究段階であり、ゴールへの道のりはまだまだ遠いと言わざるを得ません。しかし技術開発本部は大きな夢を描き、その実現へ向けてチャレンジする部署だと私は思っています。
医療分野でのAI活用は社会的にも価値があるものです。ゴールは遠くても、我々がひとつひとつ成果を積み上げていくことで社会的認知を高めていくことが重要だと考えています。共同研究先である杏林大学内では倫理審査も通過して、個人情報データをフルオンラインで臨床研究に使用する目処もつきました。臨床の場での研究の積み重ねや法的整備を含め、時間はかかりますが、今後は大学の先生方の活動をサポートしていきたいと考えています。
個人的には、研究開発の視点からこの技術を様々なプロジェクトに応用していきたいです。そのために、まずはAIをはじめとする技術の知見を深め、契約やチームマネジメントのノウハウを身につけることを当面の目標にしています。

他のプロジェクトメンバーの視点
-
 契約担当
小倉 正彦
技術開発本部ヘルスケアAIセンタ
契約担当
小倉 正彦
技術開発本部ヘルスケアAIセンタ
電子情報学類卒業。2017年入社。2020年4月にプロジェクト参画。研究計画立案支援および倫理審査対応を担当。新型コロナウイルス感染拡大により、附属病院内で予定されていた実証実験をNTT DATA内で行うことになり、個人データである患者動画の取り扱いなど、プロジェクトを推進するうえで必要な契約関連業務を担当。
このメンバーのインタビュー -
 アプリケーション開発担当
小山田 幸平
技術開発本部ヘルスケアAIセンタ
アプリケーション開発担当
小山田 幸平
技術開発本部ヘルスケアAIセンタ
システム情報科学府情報学専攻。2020年入社。入社して最初の配属先がヘルスケアAIセンタで、配属と同時にプロジェクトに参画した。プロジェクト最年少メンバーだが、アプリケーション開発のほか、共同研究を行う杏林大学との折衝、調整窓口やプロジェクトの進捗管理など、プロジェクトの推進役を担っている。
このメンバーのインタビュー
※掲載内容は取材当時のものです